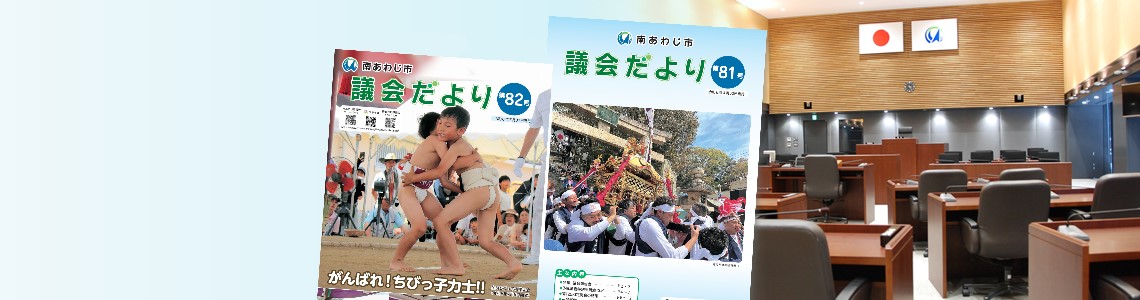本文
令和6年度政務活動費【つなぐ】
政務活動費収支報告書(令和6年度)
会派名 : つなぐ
1.収入
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 政務活動費 |
50,000円 |
2.支出
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 調査研究費 |
35,220円 |
|
| 研修費 |
0円 |
|
| 広報広聴費 |
10,000円 |
|
| 要請・陳情活動費 |
0円 |
|
| 会議費 |
0円 |
|
| 資料作成費 |
0円 |
|
| 資料購入費 |
0円 |
|
| 事務費 |
2,978円 |
|
|
計 |
48,198円 |
3.残額
残額 1,802円
4.調査研究の成果
福井県大飯郡高浜町 日時:令和7年1月21日(火)
【相手方】
海業施設(取組みと施設見学)
【目的・内容・結果等】
高浜町は総人口が9,546人。うち65歳以上が3,238人(高齢化率33.9%)山林が町の面積の約70%を占めている。
関西電力高浜原発のある町であるが、発電所ができたことにより産業構造が大きく変化して、漁業が衰退し担い手不足も深刻となっている。
夏場はまだ栄えているが、冬場の日本海の天候は厳しく、訪れる観光客も減少し、カニ、ふぐなどの新しい特産料理を工夫しているが施設の老朽化もあり、新たな客層の獲得には成功していない。
こうした状況の中、漁業の振興を目指し平成21年(2009年)よりスタートしたコンパクトシティ構想が打ち出され、高浜漁港再整備基本計画を策定。
順次事業化を進め多様で魅力ある漁業計画と地域づくりを計画し完了させ漁業再生のため魚の価値を上げるために、生産者が取ってきた魚を加工して販売する海の6次産業施設「UMIKARA」を施設設計、令和2年運営会社「まちから」を設立、令和3年UMIKARAをオープン。現在、販売施設、加工施設、荷捌き場の整備管理、漁港の新築移転など順次行い高浜6次産業化事業の見える化がスタートし、本格的な海業の発展の基盤を確立させている。
特産品開発にも力をいれており、手のひらサイズの「イワガキ養殖」のブランド化に向けた取組も注目したい。
UMIKARA施設周辺で毎月開催される「昼市」やイベント開催で猟師らが参加することで住民と漁業が身近になり定期的な開催による賑わいの定着化が期待される。
水産振興に専門の女性幹部を配置し、女性ならではの目線でまちのバックアップ体制を確立している。
海業の成功の秘訣は、人材の投入といっても過言ではないと思う。
【今後の課題・取り組み等】
課題として、後継者の確保、魚価の向上、冬場の客確保、など当面の課題は多いが海にまつわる取組み(海業)と言っても様々な形態があり、地域性もあり漁港によって、また漁協によって課題や手法、具体的な計画は多様となる。南あわじの漁港関連の海業も多種多様とならざるを得ないであろう。個性豊かな海業の展開が期待される。
南あわじ市では丸山漁港が先行していると思われるが、他にも湊、福良、阿万、灘、沼島漁港など地域の特性を活かし、地元漁師の積極的なイメージ作りを進める政策提案をしていきたいと思う。
南あわじ市も漁業の後継者不足の問題は深刻であるが、親の後を継ぐのはもちろんU・Iターンや移住者など、如何にして新規参入者を増やしていくのかが課題だと思う。


滋賀県高島市 日時:令和7年1月22日(水)
【相手方】
高島浄化センター
【目的・内容・結果等】
汚水を浄化する過程で発生する下水汚泥から肥料を製造する「高島浄化センターコンポスト化施設」を見学。
高島浄化センターで発生した汚泥は県外で処分されていたが処分費用が高騰しその対応を滋賀県下水道審議会で何回も論議を重ねた結果「処理方法はコンポスト化が適当」と知事に答申した。
日本下水道事業団が設計し、県が施設整備を進め、2024年に完成した。
下水汚泥は、固形燃料や建設資材など様々な有効活用ができるが、高島浄化センターでは肥料にすることで地産地消や資源循環を実現した。
コンポスト化施設では、汚泥に空気を吹き込みながら定期的な撹拌を行い、約40日かけて微生物の力により、日量10トンの汚泥処理で1トンの肥料ができる。
当初予定の大量販売ではなく、必要な方に量り売りをしている。資源リサイクルという観点から素晴らしい取り組みである。
一方で、施設はかなり広い敷地ではあるが、風向きによって悪臭対策をどう克服するかが課題だと思う。
【今後の課題・取り組み等】
県が主体となった事業であるが、南あわじ市で実施する場合、かなり広い土地が必要である。財源を確保して、安定的な運営が出来るようにする必要がある。
南あわじ市では下水汚泥の処理に加え、玉ねぎなどの野菜残渣処理、生ゴミなども併せて処理する方式が必要でないかと思われる。
バイオマス事業の模索が続く南あわじ市であるが、高島市の事例も参考に、事業化を目指していくことが必要である。




灘黒岩水仙郷・灘市民交流センター 日時:令和7年2月17日(月)
【相手方】
南あわじ市
産業施設部 興津武秀 副部長 井上拓也 副部長
商工観光課 土井正典 課長 金山悠輝 主事
建築技術室 榎勢 陽一 室長
【目的・内容・結果等】
灘黒岩水仙郷のリニューアルオープン後の状況と今後の課題について政務調査で福井県越前水仙ランドへ視察に行ってきた事を参考に灘黒岩水仙郷の今後の管理運営計画について意見交換をした。
1.まず水仙の花を咲かすことが絶対条件である。園地の土壌改良、土留め等地元の意見を聞き参考にする。
2.園路の階段は高齢者や障害者に対して優しくない。落石防止もあるとの事だが手すり等改善が必要と思う。
3.2階テナントに土産物や切り花などの物販が少ないので、もっと充実すべきだと思う。観光客からも土産物が少ないとの声あり。
【今後の課題・取り組み等】
1.冬場の水仙シーズンはもちろん、通年営業とするなら2階テナント事業者と連携して灘黒岩水仙郷でしか食べることができない食材を使った看板メニューの開発等を進める。
2.灘地区は、魅力的な観光資源があり温暖な気候と海が見える景色は抜群である。体験コンテンツ等、地域の活性化に寄与できるよう進める事が重要と考える。
3.夏場の海洋レジャー、キャンプ、ゆづるは山系の登山客の取り込みなどを考える。
4.シカ、イノシシ等の鳥獣対策も重要な課題である。
5.球根は灘地区で養生していくほか、市内からも提供していただき、灘水仙振興会と連携して球根の間引きや植付け作業などを行う。
6.屋上をイベントだけにするのはもったいない!春夏秋冬の花を楽しめる空間を創出する。


市地区公民館 日時:令和7年3月16日(日)
(目的)
深刻化する不登校・ひきこもりについて、不登校を「ネガティブな問題」として捉えるのではなく、子どもたちの幸福や自立を支えるために何ができるかを考える。
(内容)
不登校に悩む保護者の方、支援に関わる方、教育関係者に呼びかけ、講師に山田良一教授(高千穂大学人間科学部教授)をお迎えして講義を基に意見交換を行う。
(結果等)
会場参加者33名(主催者側含む)・オンライン参加5組
70分程度の講演の後、休憩を挟んで約1時間の質疑応答を行った。
守本憲弘市長、喜田憲和副市長を始め、市役所職員や市内外の社会福祉協議会関係者、教職員にも参加していただき、有意義な意見交換ができたと考える。
講演の中で、大人は気分転換や、ストレスの解消を知っているが、子どもはストレスを抱えたまま発散できない。子どもなりに心配をかけないように「がんばる」この「がんばり」が切れると学校にいけない、行きたくない。まずは子どものストレスの要因を知ることが大切だと考える。
山田教授の講演(質疑応答は除く)は、ケーブルテレビネットワーク淡路が撮影しており、後日放映されるので、多くの方に視聴いただきたい。
【備考】
主 催:南あわじ市議会ゆづるはクラブ
共 催:創世クラブ・つなぐ
参加議員:中村三千雄、原口育大、木場 徹、久米啓右、長江和代、蔭山順子、熊田 司、吉田良子