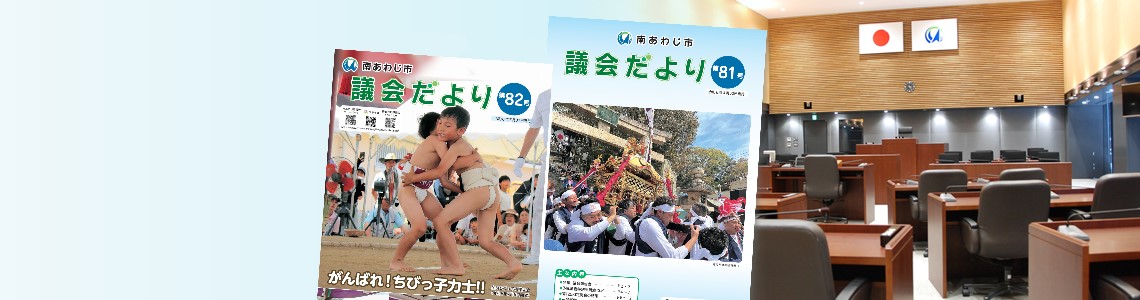本文
令和5年度政務活動費【大志クラブ】
政務活動費収支報告書(令和5年度)
会派名 : 大志クラブ
1.収入
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 政務活動費 |
150,000円 |
2.支出
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 調査研究費 |
113,511円 |
|
| 研修費 |
0円 |
|
| 広報広聴費 |
0円 |
|
| 要請・陳情活動費 |
0円 |
|
| 会議費 |
0円 |
|
| 資料作成費 |
0円 |
|
| 資料購入費 |
0円 |
|
| 事務費 |
35,703円 |
|
|
計 |
149,214円 |
3.残額
残額 786円
4.調査研究の成果
南あわじ市議会視察団 岩手・青森県研修 日時:2023年10月2日・3日・4日
岩手県葛巻町(10月2日)
〇「酪農の現状と課題について」
葛巻町は岩手県の北部に位置している。
人口5,510人で2,656世帯で面積は434.96平方kmでうち86%が森林である。
平均気温は8.8℃の酪農と林業の町である。
・平成25年に(新葛巻型酪農構想)を立ち上げた背景、きっかけ、経緯について
昭和44年に新全国総合発展計画で、大規模畜産プロジェクト地域に全国3地域の一つに選定された。
葛巻町の公共牧場として社団法人葛巻町畜産開発公社を設立して日本一の公共牧場「くずまき高原牧場」が出来る。
昭和50年に農用地開発公団が、北上山系広域農業開発事業として実施された。
このような経過で新葛巻型酪農構想策定された。
・(新葛巻型酪農構想)を策定してから10年が経過しましたが、コロナ禍やウクライナ情勢に伴う
燃料・飼料高騰などを経て、葛巻町の酪農の現状と課題はどのようになっているのかお教えいただきたい。
酪農が町の基幹産業で乳業工場など酪農関連産業が町の雇用を支えている。
人口減少や少子高齢化による後継者や労働力不足、設備の老朽化。酪農家の戸数は減少傾向である。
地域の酪農を支える人材の育成・確保。
〇エネルギー政策の現状と課題について
・葛巻町の「新エネルギー宣言」について
平成11年6月に「新エネルギー町・葛巻」を宣言した。「天のめぐみ」である風力や太陽光、
「地のめぐみ」である畜産ふん尿や水力、そして豊かな風土・文化を守り育てた「人のめぐみ」を
大切にしながら、町民一体となってグリーンでリサイクル可能な新エネルギーの導入に積極的に
取り組んでいくことを誓い宣言した。
・新エネルギー関連施設の施策について
山間高冷地に吹く風を利用して風力発電所を34基設置
公共施設の空きスペースを利用して太陽光発電所の設置
家畜排泄物から発生するメタンガスを利用してバイオガスを有効利用
森林整備の際に発生する間伐材で木質バイオマスガス化発電設備の設置
チップ製造の過程で発生する樹皮でバークペレットでボイラーやストーブの導入
・コロナ禍やウクライナ情勢に伴う燃料・電気代等の価格高騰によるエネルギー政策への影響について
電力自給率:約360% (総発電量:約14,900万kWh 全力消費量:約4190万kWh)


青森県弘前市(10月3日)
弘前市は、青森県の南西部に位置し、総面積524.2平方kmの内陸型地域である。
日本で最初に市制を施工した都市の一つである。人口16万2000人ほどのまちである。
青森県の基幹農産物であるりんごの約4割を生産する樹園地が広がり、さらに、その地域を取り巻くように山林地帯が伸び、緑豊かな自然環境に恵まれている。
〇農福連携について
・高齢化と後継者不足で働き手が不足している農業において、障害者が活躍する仕事の切り出しを行うこととなった背景、きっかけ、経緯について。
農業分野と福祉分野が連携し、障がい者等が農業生産活動に関わることで、農業分野における新たな働き手の確保につながるだけでなく、障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すことが期待される取り組みである。
・農作業を季節ごとに、体系的にわかりやすくまとめた「農福連携カレンダー」を用意したことで得られた効果
(農福連携数の増加など)について。
農作業繁忙期の人手の確保や人手不足によりこれまで実施できていなかった作業ができる。作業の細分化による、作業工程の見直しで作業の効率化が計れるようになった。就労機会の拡大や社会との関わりによるコミュニケーション能力の向上が見られる様になった。
・農福連携への新規参入や障がい者が農作業を行う上で課題解決を支援するために実施の
「お試しノウフク・シェアノウフク」の効果、実績について。
・市が労働力不足の解消を図るため、あなたに農福連携に取り組む農業者等の障がい者雇用に要する経費一部を補助することで農業者7名が障がい福祉事業所4事業所とマッチングし農業者1名が障がい者1名の直接雇用を実施し、りんご・ニンニク作業の計18作業を実施し延べ1010人の障害者の雇用機会を創出した。

青森県大鰐町(10月4日)
青森県津軽地方の南端部に位置する大鰐町の面積163.43平方kmは、豊かな自然と緑に恵まれている。人口は、8,549人であり行政面積のうち大部分の112.66平方km約69%を森林でしめている現状である。
○津軽南地区農業者向け出会いの応援事業について
・「あおもり出会いサポートセンター」が運営するマッチングシステムを利用する津軽南地区
(黒石市、平川市、藤崎市、田舎館村、大鰐町)の農業者の方々に対し、登録料等の一部を助成することと
なった背景、きっかけ、経緯について
事業主体は、津軽南地区農業委員会連絡協議会が事業名 (令和五年度農業後継者花嫁・花婿対策事業 )と名づけ2年に一回の頻度で農業者の出会いのための「婚活授業」を実施している。令和五年度の予算編成に先立ち、構成市町村の農業委員会会長、事務局長会議が開催され、婚活事業の復活、予算計上について本協議会事務局として、40万円規模のイベント系事業を提案したところ厚生市町村から一つの意見として、その場限りいわゆる形式的なイベントで終わることから費用効果があまり期待できず、各市町村から貴重な財源を本協議会の負担金そして運営することを踏まえ、授業のあり方について検討を要することとなった。これを契機に構成市町村の農業委員会局長からの提言もありイベント系以外の効果的な方法として農業者の方に対する直接的な助成事業として構築することに至った。
・大鰐町における今後の農業の諸課題について
大鰐町の農業の現状は、3方を山に囲まれた地形にあることから、内陸型気候の特徴を示しており、水稲とりんごを基幹作目とした、野菜、花き、果実などを複合作目として発展している。、りんごは、優良品種の栽培や輸出市場の拡大等もあり、販売額が堅調に推移しているが、山間傾斜地であるため、労働力の高齢化や担い手不足が話題となっている。野菜については近年、少ない面積でも収益性の高い大鰐高原トマト、メロン、きゅうりといった施設園芸の若手生産者が増えている。