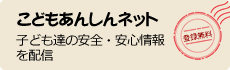本文
乳幼児等医療費助成制度
保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。
助成対象
対象者
健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入している南あわじ市在住の0歳~小学3年生(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児等
所得制限
0歳児:所得制限なし
1歳~小学3年生:保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計額が23万5千円未満であること
- 市民税の所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・ふるさと納税ワンストップ控除適用前の金額です。
- 税制改正により廃止された年少扶養および特定扶養親族の扶養控除見直し前の旧税額を適用して判定します。
- 指定都市で市民税が賦課される場合(税率8%)、指定都市以外に住所を有する者とみなし所得割額(税率6%)で判定します。
- 保護者がお子さまの生計を維持できないときは、扶養義務者(祖父・祖母等)の所得で判定します。
- 毎年所得の見直しがありますので、更新時に所得要件に当てはまる方が対象となります。
申請の手続き
お子さまが生まれた時は、申請手続きを行ってください。(受給者証は自動的に発行されませんのでご注意願います)
申請場所
総合窓口センター(市役所本館1階)または沼島出張所
- お子さまのマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
医療機関等窓口で提示いただくもの
兵庫県内で受診される際は、医療機関等にてマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書と乳幼児等医療費受給者証等を提示してください。
一部負担金
|
対象者 |
自己負担限度額 |
|
|---|---|---|
|
外来 |
入院 |
|
|
0歳~小学3年生 |
負担なし |
負担なし |
※保険診療以外の医療費(健診、予防接種、診断書料など)および入院時の食事代などは助成の対象となりません。
限度額適用認定証
入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を加入されている健康保険の保険者へ申請いただき、交付を受けた後、医療機関の窓口で提示してください。
※南あわじ市国保の方は、総合窓口センターにて申請手続きをお願いします。
(南あわじ市国保以外の方は、加入されている健康保険にお問合せください。)
※ただし、保険税の納付状況等により、交付されない場合があります。
福祉医療費助成における注意点
- 生後1ヵ月乳児健診、ビタミンK2シロップの投与、保険適用外の自費診療分は福祉医療費助成の対象となりません。
- 学校等の事故で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合は、福祉医療費助成の対象となりません。
- 令和3年7月1日より訪問看護療養費が福祉医療費助成対象になりました。
- 県外で受診された場合は受給者証が使えませんが、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
●福祉医療費助成対象の方へ● [PDFファイル/104KB]
医療費の払い戻しの手続き
- 兵庫県外の医療機関等で受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
- やむを得ず、乳幼児等医療費受給者証を提示せずに医療機関等で受診されたとき
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療等)を適用して一部負担金を払ったとき
申請に必要なもの
- 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)
- お子さまのマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書
- 乳幼児等医療費受給者証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
- 治療用装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書
支給申請の際は下記ファイルをご利用いただけます。
福祉医療費支給申請書 [Wordファイル/27KB]
他の公費負担医療制度との併用
乳幼児等医療の受給者で、次の公費助成制度の受給者は、自己負担額を助成します。
- 自立支援医療(育成医療)
- 小児慢性特定疾病医療
- 難病法に基づく特定医療
※保険診療以外の医療費及び入院時の食事代は、対象外
助成手続きについては、医療機関の窓口で公費助成制度の自己負担額をお支払いいただき、後日、総合窓口センターで払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
- 公費負担医療の自己負担額領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)
- お子さまのマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書
- 対象となる公費助成制度の受給者証等(公費助成制度の種別がわかるもの)
- 乳幼児等医療費受給者証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 支給決定通知書(健康保険または対象となる公費助成制度の実施機関から還付がある場合)
支給申請の際は下記ファイルをご利用いただけます。
公費負担等医療費支給申請書兼請求書 [Wordファイル/76KB]
転入の場合
- お子さまのマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 1月2日以降に南あわじ市に転入した場合は、1月1日時点で住民票のあった住所地の所得・課税証明書(最新の年度分)が必要です。なお、申請時期によっては前年度分も必要となります。
※所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可。
※保護者(父・母両名分)の所得・課税証明書が必要です。
※お子さまを扶養しているのが両親以外(祖父母等)で、南あわじ市外に在住の場合、その方の所得・課税証明書が必要です。