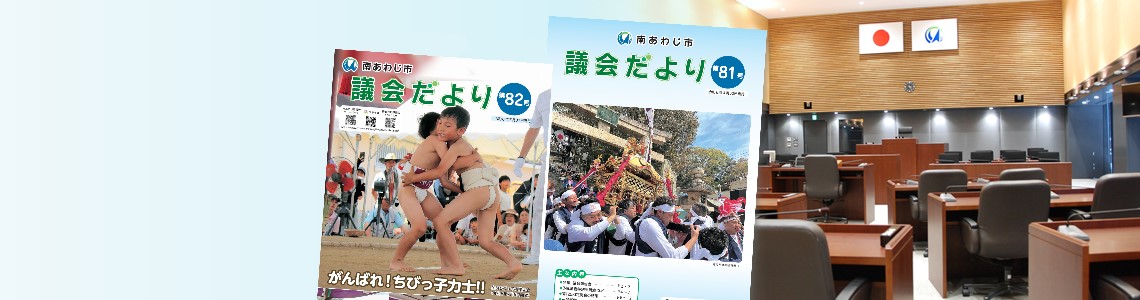本文
令和6年度政務活動費【誠道クラブ】
政務活動費収支報告書(令和6年度)
会派名 : 誠道クラブ
1.収入
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 政務活動費 |
300,000円 |
2.支出
|
金額 |
摘要 |
|
|---|---|---|
| 調査研究費 |
111,178円 |
|
| 研修費 |
9,000円 |
|
| 広報広聴費 |
0円 |
|
| 要請・陳情活動費 |
0円 |
|
| 会議費 |
0円 |
|
| 資料作成費 |
0円 |
|
| 資料購入費 |
0円 |
|
| 事務費 |
0円 |
|
|
計 |
120,178円 |
3.残額
残額 179,822円
4.調査研究の成果
南あわじ市議会視察団 大阪府・富山・岐阜県研修 日時:2024年11月11日・12日・13日
視察報告
※11月11日 大阪府住之江区 日本国際博覧会協会
大阪住之江区咲州庁舎内の日本国際博覧会協会にて視察を行う。まずは大阪・関西万博の概要について説明を受けた。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、サブテーマに、「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」を据えて取り組んでいる。会場の夢洲388haのうち155haを使用し設営し、約2820万人の来場者を想定する。そのうちインバウンド人口は350万人としている。開催意義としては、万博という場で世界が1つになることに意義があり、いのち輝く未来社会のありようを共有することとしている。そして、この大阪・関西万博を契機として、世界の多様な文化、価値観を交流し創造が促進されていき、経済や社会、文化等あらゆる面において、日本全体にとって更なる飛躍の契機となることを狙っている。目玉として世界161ヵ国によるパビリオンがある。47の国が独立してパビリオン運営を行うが、他の114ヵ国は共有スペースにてパビリオン運営を行う。そこでマスコミ報道でもされて心配されている工期に関しては、開幕に合わせてハード面の建設はなんとか間に合うレベルであるが、ソフト面では開幕時には間に合わないパビリオンも見られるとのことである。メイン会場の木製リングは先月に開通し順調に工事が進んでいる模様。開催5ヶ月前の現在の課題や問題点としては、関西にいると感じないが日本全体で見るとまだまだPR活動が足らないということである。今後とも日本全国に向けてPR活動が必須である。我々周辺地域の自治体の者としても、今後万博のPRの後押しや、万博だけでなく淡路地区、南あわじ市まで含めた観光一大ツアーとして関西全体を盛り上げて行く必要がある。安全面で一番心配されているメタンガス爆発事故に関しては、3つの合言葉!止める→逃がす→測るの「発生を抑制」「強制換気」「リアルタイム測定」で安全管理に努めるとのことであった。
南あわじ市としては、万博観光に来られた人を地元に引き込めるように魅力ある施設、まちづくり、プランの策定をしなくてはならない。この一大イベントに乗り遅れることなく「行きたくなる市」「魅力溢れる市」づくりを進めて行かなくてはならない。行政だけでなく民間も含めて広く意見や情報を集めなくて取り組むことが必要であると考える。来年度、大阪・関西万博の成功を祈るばかりである。
大阪万博博覧会協会にて視察風景↓↓

※11月12日 富山県砺波市 休日の学校部活動の地域クラブへの移行について
富山県砺波市は人口約47000人の長流「庄川」が貫流する富山県西部の礪波平野に位置する市である。現地にて、休日の学校部活動の地域クラブ活動への移行について視察してきた。
中学校数は4校で生徒数は約1300人程度、南あわじ市とは違い全学生が部活動に属することが条件となっている。教育委員会の生涯学習・スポーツ課が指揮を取り地域クラブへの移行に関するすべての業務を担っている。平日は学校の部活動とし休日の活動を地域クラブへと移行を進めている。進める上で一番大切な地域クラブであるが、元から砺波市には部活動とは別に地域クラブが存在していた為、案外スムーズな移行が進んでいる模様。しかし、説明会などを4、50回開き保護者やクラブへの説明をして理解を求めている。地域クラブへ派遣する指導者にも1時間1600円の謝礼金をマックス3時間分支払い、その財源は国からの助成金半分、市の負担が半分と行政が教育に力を入れて子供を取り残さないという姿勢が見えて教育熱心な市である印象を受けました。今後の課題としては、各クラブが活動場所の取り合いにならないように調整する事、とくに雨や冬にそういったトラブルになる傾向があるので、担当課の方で調整がスムーズに出来るようにしなければない。さらに持続して活動出来るように補助制度の確立と財源の確保、学校施設を利用するにあたり、先生が開錠施錠するために早朝夜間、休日に出勤してこなくてはいけないということや、地域移行の大きな目的である教員の働き方改革になっていないということが、今後改善が必要と考えられる。南あわじ市が進めている地域移行とは全く異なり、正直驚いたと同時に、南あわじ市でも担当課を設置して今後方向性も含めて、部活動の地域移行を進めていかなくてはならないと感じた。今回砺波市を訪問するまでは南あわじ市は地域移行が進んでいる方だと過信していたが全く違った。何が大切で何を中心に物事を進めていくのか、根本的なことを改善しなければ南あわじ市の地域移行など進まないと思った。2026年からは平日の地域移行が進められて、改革推進期間から改革実行期間に移ります。周りから取り残されないように島内3市は連携を取りながら地域移行を進めていかなくてはならない。今回視察して学んだことは今後自身の活動に活かしていきたい。
※富山県砺波市 砺波図書館おたすけ隊について
部活動の地域移行化に引き続いて、砺波図書館おたすけ隊について視察した。砺波図書館は敷地面積7500平方メートル、延床面積3342平方メートル、総事業費22億円、29万冊の蔵書数を誇る地上2階建てのワンルーム構造の図書館で、冷暖房は地中熱を利用して省エネルギー化にも努めている。図書館自体はセルフ貸出や予約システム、自動返却などICタグを利用してBDSゲートで入場管理をし、平日は約600人土日は約800人が訪れる施設である。そんな砺波図書館に、おたすけ隊があり、「美化部」「広報部」「園芸部」「ゲーム部」と4つの部門で構成され、ボランティアで約75名の方が参加されている。特にゲーム部は世代間交流の目的でスタートしたが現在では30名ほど毎回集って盛り上がり、2024年図書館アワードの大賞を受賞した。その他にも図書館友の会があり、ただの読み聞かせでなく、英字新聞や源氏物語、俳句、幼児など幅広く11の会で構成されて読書推進の一役を担っている。子供たちの本離れを食い止める為にも児童書が7万冊、障がい者用の本なども充実していて、まさにこの図書館のコンセプトである「学びをつなぐ」の通り、地域の元気や個人の幸せにつながる施設として評価できるものだと感じました。南あわじ市においても、立派な図書館はあるが市民が親しみ活用されているかと言えば必ずしもそうではない。宝の持ち腐れではないが、やり方によっては図書館で地域を盛り上げることも可能である。ただ本を貸し借りする施設ということではなく、地域を元気にする図書館として活用していかなくてはならない。それが「まちの活性化」にもつながると思う。今回視察した事を持ち帰って提案したいと思った。
砺波図書館にて視察模様↓↓↓ 砺波図書館の風景↓↓↓


※11月13日 岐阜県大野郡白川村 小中一貫教育の取り組みについて
南あわじ市だけでなく日本における急速な少子化は、次代を担う子供達の健やかな成長にとって望ましい環境を整えることなど、多くの課題を抱えている。そんな中、義務教育学校「白川村立白川郷学園」にて小中一貫教育の取り組みについて視察。学校教育目標として「ひとりだち」を掲げ、義務教育9年間を見通した途切れることのない一貫した指導方針のもと、一人ひとりの子供が着実に学力を身につけて、心身共に健全で豊かな人間性と地元を愛する心、社会性を発揮できるように実践している。教育課程は低、中、高(1~4年生、5・6年生、7~9年生)のブロック制を導入して、低ブロックでも一部教科担任制を行っている。学校での職員間の意志疎通だけでなく、地域の方々も参加し意見交換等が活発に行われて授業や学校活動が非常に行いやすい環境があり、教育の質の高さを実感しました。小中一貫教育を実践していく中で見えてきた成果としては、確かな学力の定着が見られる。ふるさと学習や英語学習など9年間一貫して取り組める。一貫教育は教員の質の向上、授業力向上につながっている。などが挙げられる。課題としては、教員が3年で移動になることや、地域とのつながりがやや薄くなってくる。などが挙げられるが、教員の移動に関しては、教員間での引き継ぎや自身の教育に対する意識の高さでカバーし、地域との関わりについては、学校運営協議会(コミュニティスクール)を立ち上げて学校と地域が一体となり人を育てる!という一体感をもって取り組んでいる。地域が積極的に関わり意見を言い、力を貸すことによって学校(教員)は変わり、学校が変わると子供も変わり、子供が変わると地域が変わる!といういいサイクルで村自体が回っているように感じた。白川村の事例は、学校施設整備が先行しての改革といった面もあり、小規模自治体の小規模校であるから実現できたという面もあるかもしれないが、それでもこれからの人口減少社会の中では、こういった取り組みの成果を波及させていくことが必要であると感じた。南あわじ市においても予想をはるかに越えるスピードで少子化が進んでおり、出生数の減少は深刻である。未來ある子供達の教育環境を考えると、小・中学校の再編は喫緊の課題であり、南あわじ市としても教育のあり方として検討していくべきであると思う。今回視察し、学んだことは今後の議員活動に生かしていく。
白川郷学園にて視察風景↓↓